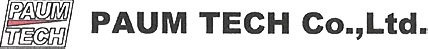『空き家問題』解決に挑む本の執筆をしながら気づきました。
『空き家問題』解決に挑む本
執筆をしながら気づきました。
令和5年の日本は「少子社会」と「高齢社会」になっています。新聞やテレビでは「少子化」とか「高齢化」という言葉を見聞きしていますが「・・・化」を通り越しています。「少子化」という言葉は、内閣府のホームページで、=「広辞苑」(岩波書店)では(中略)「1992(平成4)年度の国民生活白書で使われた語」と、言葉の出所まで明記している。(中略)政策課題として取り上げられるようになったのは、1990(平成2)年のいわゆる「1.57ショック」からである。1966年(昭和41年)「丙午」の合計特殊出生率1.58より低い戦後最低の1.57と発表されたことが契機となった。=と説明しています。今年は2025年(令和7年)です。「少子化」という出生率の低下が社会的な関心を集めてから35年の年月が流れています。日本の人口も減り続けています。空き家は増え続けています。知恵の出しどころかな・・・。
総務省の国税調査による人口と世帯数の推移
人口と世帯数の実績値と推計値の折れ線グラフを見つけました。日本の人口のピークは2008年(平成20年)でした。世帯数のピークは2023年(令和5年)と推計されていて、人口も世帯数もピークから下がり続ける推計が一目瞭然です。日本では「住宅が余っている」と昭和の時代から言われ始めたことは先で触れました。政府の記録では1968年(昭和43年)です。国の政策で新築住宅に手厚い補助や、厳しい決まりが目白押しです。新築住宅ばかりに重きがおかれてきたせいなのか、中古住宅には人気がないように見受けられるのも仕方ないのかも知れませんね。1960年代から国民の世帯数を家の数を追い抜いた「住宅が余る」のが空き家問題の根本になっていると感じています。そんな空き家問題に挑むブログを毎週書いていきます。そして、空き家にさせないための本も出版して全国の書店やAmazonで販売されています。あなたの家が空き家になってからではなく、空き家になる前の現在(いま)だからこそ「できることがある」と多くのヒントを満載してあります。あなたの子どもは、あなたがそうしたように自信が生まれ育った家には戻って暮らすことはないと思うのですが・・・。
日本の国としての空き家対策を探ってみると
空き家問題の対策は「ハード」面と「ソフト」面で考えることが肝になっています。空き家は文字通り「家」(住宅)なので「ハード」面での対策が色濃く出ているのが国土交通省の施策です。省内ではいろいろさまざまな対策を組み立てて「ハード」としての空き家を如何にして有効に活用して減らしていくのか知恵を絞っているように感じます。「ソフト」面では、厚生労働省も空き家対策を打ち出しています。福祉の視点で空き家を活かしていく施策として「安心して地域で暮らせる住まいと支援の確保策」がありました。地域支援として空き家や空き部屋を活用する施策でした。もうひとつ総務省でも空き家の対策に関わっていました。ここでは「空き家対策に関する実態調査」の結果報告として、他省庁の空き家対策を外部から見るという立ち位置のように感じました。さて・・・こうした関係省庁によるそれぞれ独自(縦割りな?)対策が空き家問題の解決につながっていくのかしら・・・。
『空き家問題』対策の対象の家は「戸建ての家」
我が国日本が国として『空き家問題』のターゲットにしているのは「戸建ての家」で、その家が「築古の家」で、「木造の家」で・・・と「空き家をなんとかしなければいけない」その対策を絞り込んでいるように感じませんか・・・。ここで疑問に感じるのは「マンションはどうなんだろう?」です。最近では同世代のファミリー世代が集って住まう「集合住宅」(マンション)が多くなっていますが、住宅不足の時代にも「ニューファミリー」と呼ばれた若い世代の家族が同じように集って住み始めたマンションも子どもたちが独立して夫婦ふたりきりになっています。「ニュータウン」が「オールドタウン」と自嘲気味に?呼ばれるようになっています。こうしたマンション住戸の『空き家問題』はどうなるのでしょう・・・。マンションでは戸建ての家のような「近所迷惑なこと」(倒れそうとかゴミ屋敷で物騒とか火事が怖いなどなど)はさすがに見聞きしたことはありませんが・・・、マンション住戸だって家には変わりがないと思います。